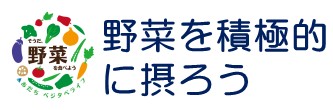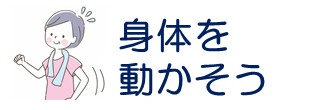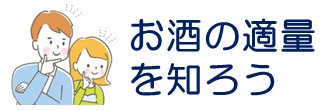ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 健康診査(検診・検査) > 健康診査(検診・検査)トップページ > 生活習慣病を予防する8つの秘訣!
ここから本文です。
公開日:2020年11月27日 更新日:2025年2月3日
生活習慣病を予防する8つの秘訣!
 生活習慣病は自覚症状がなく進行していく、いわば「見えない敵」です。症状が現れたときには、かなり悪化している可能性があります。
生活習慣病は自覚症状がなく進行していく、いわば「見えない敵」です。症状が現れたときには、かなり悪化している可能性があります。
早めの生活習慣の改善があなたの未来に大きく影響します。
健診の結果や生活習慣で1つでも気になる項目があったら、8つの秘訣を参考に、生活習慣を見直してみませんか?
野菜を積極的に摂ろう
野菜から食べる(ベジファースト)
ご飯などの糖質主体の食べ物を急に食べると、血糖値が急上昇します。血糖値の急上昇は、すい臓から「インスリン」というホルモンが過剰分泌されて脂肪をため込みやすく、動脈硬化や生活習慣病の要因となります。
食物繊維が豊富な「野菜」から食べることで、血糖値の急上昇を抑え、糖尿病をはじめ、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの生活習慣病の予防に役立ちます。
また、野菜を先に食べることで満腹感も得られやすくなるため食事量(摂取カロリー)を減らす効果も期待できます。
野菜は1日350グラムを目標に
 野菜はビタミン、ミネラル、食物繊維など身体に必要な栄養素を含んでおり、生活習慣病予防に欠かせません。加熱調理で体積を減らしたり、そのまま食べられる野菜(きゅうり、トマトなど)を選ぶ、コンビニ・スーパーなどの惣菜(野菜が入っているもの)を活用することで目標達成に一歩近づくことができます。
野菜はビタミン、ミネラル、食物繊維など身体に必要な栄養素を含んでおり、生活習慣病予防に欠かせません。加熱調理で体積を減らしたり、そのまま食べられる野菜(きゅうり、トマトなど)を選ぶ、コンビニ・スーパーなどの惣菜(野菜が入っているもの)を活用することで目標達成に一歩近づくことができます。
ちなみに食物繊維には整腸効果だけでなく、血糖値の上昇を抑制したり、血液中のコレステロール濃度の低下、ナトリウムの排出など糖尿病や高血圧症の予防に役立ちます。不足しがちな成分のため、意識して摂ることが重要です。
食事のポイント
決まった時間に食事をとりましょう
 忙しいと食事の時間が不規則になったり、食事を抜いてしまうことがあるかもしれません。このような食生活は、体が飢餓状態になることでエネルギーを蓄えやすくなってしまうので注意が必要です。
忙しいと食事の時間が不規則になったり、食事を抜いてしまうことがあるかもしれません。このような食生活は、体が飢餓状態になることでエネルギーを蓄えやすくなってしまうので注意が必要です。
間食や夜食を見直して
間食が習慣化されてしまっていたり、就寝前2時間以内に食事をすることで太りやすくなってしまいます。また、就寝前の食事は睡眠の質を下げることにもなるので、意識して早めに夕食を済ませることが大切です。
満腹になるまで食べないで
美味しいものはたくさん食べてしまいがちですが、腹八分目を心掛けましょう。「もう少し食べたいな」でストップするのがポイント!
ゆっくりよく噛んで食べる
ゆっくりよく噛んで食べることで、食べ過ぎを防ぎます。早食いはせずに味わって食べることが、生活習慣病予防につながります。
減塩の心掛けを
一日当たり男性は平均10.9グラム、女性は平均9.3グラム(令和元年度国民健康栄養調査)の塩分量を摂取していますが、これは厚生労働省が目標とする一日当たりの塩分量を大きく上回っています。塩分を摂りすぎることで高血圧の要因となりますので食事の際は減塩を心掛けることが大切です。食品を購入する際には、栄養成分表示で食塩相当量を確認してみるのも効果的です。
高齢期は『ぱく増し』を
 65歳以上の方の筋肉維持には、1日に少なくとも体重1kgあたり1g以上のたんぱく質をとることが望ましいと言われています。1日の目安量は肉、魚、卵、大豆製品が両手にのる位。しっかり摂取してフレイル(加齢に伴う体力や機能の低下)を予防しましょう。
65歳以上の方の筋肉維持には、1日に少なくとも体重1kgあたり1g以上のたんぱく質をとることが望ましいと言われています。1日の目安量は肉、魚、卵、大豆製品が両手にのる位。しっかり摂取してフレイル(加齢に伴う体力や機能の低下)を予防しましょう。
詳しくは『ぱく増し』は、高齢者の味方! 65歳からのたんぱく増し生活~肉も魚も食べよう~をご覧ください。
身体を動かそう
歩くことから始めよう
 運動の機会があまりなかった方が急に運動を始めるのは大変ですし、リスク(怪我や内臓への負荷)があります。また、若い頃に運動していた方でも体重の増加や筋力の低下などで思うように動けないことも。まず、今より「少しでも」歩く機会を増やすことから始めましょう。
運動の機会があまりなかった方が急に運動を始めるのは大変ですし、リスク(怪我や内臓への負荷)があります。また、若い頃に運動していた方でも体重の増加や筋力の低下などで思うように動けないことも。まず、今より「少しでも」歩く機会を増やすことから始めましょう。
エレベーターより階段を優先して
階段の上り下りは、有酸素運動の面だけでなく、手軽に足腰を鍛えることができる良い運動です。いつも乗っていたエレベーター横の階段へ一歩踏み出してみましょう。
日々の散歩を習慣に
散歩は良い運動になるだけでなく、ストレス解消効果も望めます。歩くことを習慣にすることで心身の健康をキープするのに役立ちます。
外回りの営業や荷物の運搬なども積極的に 家事でも活動量アップ!
日常生活における労働・家事・通勤・通学などの「生活活動」も身体を動かす機会になります。「生活活動」を積極的に行うことでも一日の活動量はアップします。
筋力トレーニングで効果アップ!
 歩く、家事をするなどの有酸素運動に筋力トレーニングを組み合わせることで、脂肪燃焼効果が高まります。ずっと健康でいるためにも筋力は必要な要素です。まずは、自重トレーニング(スクワットや腕立て伏せなど)から始めてみては。
歩く、家事をするなどの有酸素運動に筋力トレーニングを組み合わせることで、脂肪燃焼効果が高まります。ずっと健康でいるためにも筋力は必要な要素です。まずは、自重トレーニング(スクワットや腕立て伏せなど)から始めてみては。
※準備運動と整理運動は十分に行って、運動中は小まめに水分補給をしましょう。急に激しい運動はせず、自分にあった運動強度から始めることで長続きします。
規則正しい生活を
毎日同じ時間に起きて生活リズムをつくろう
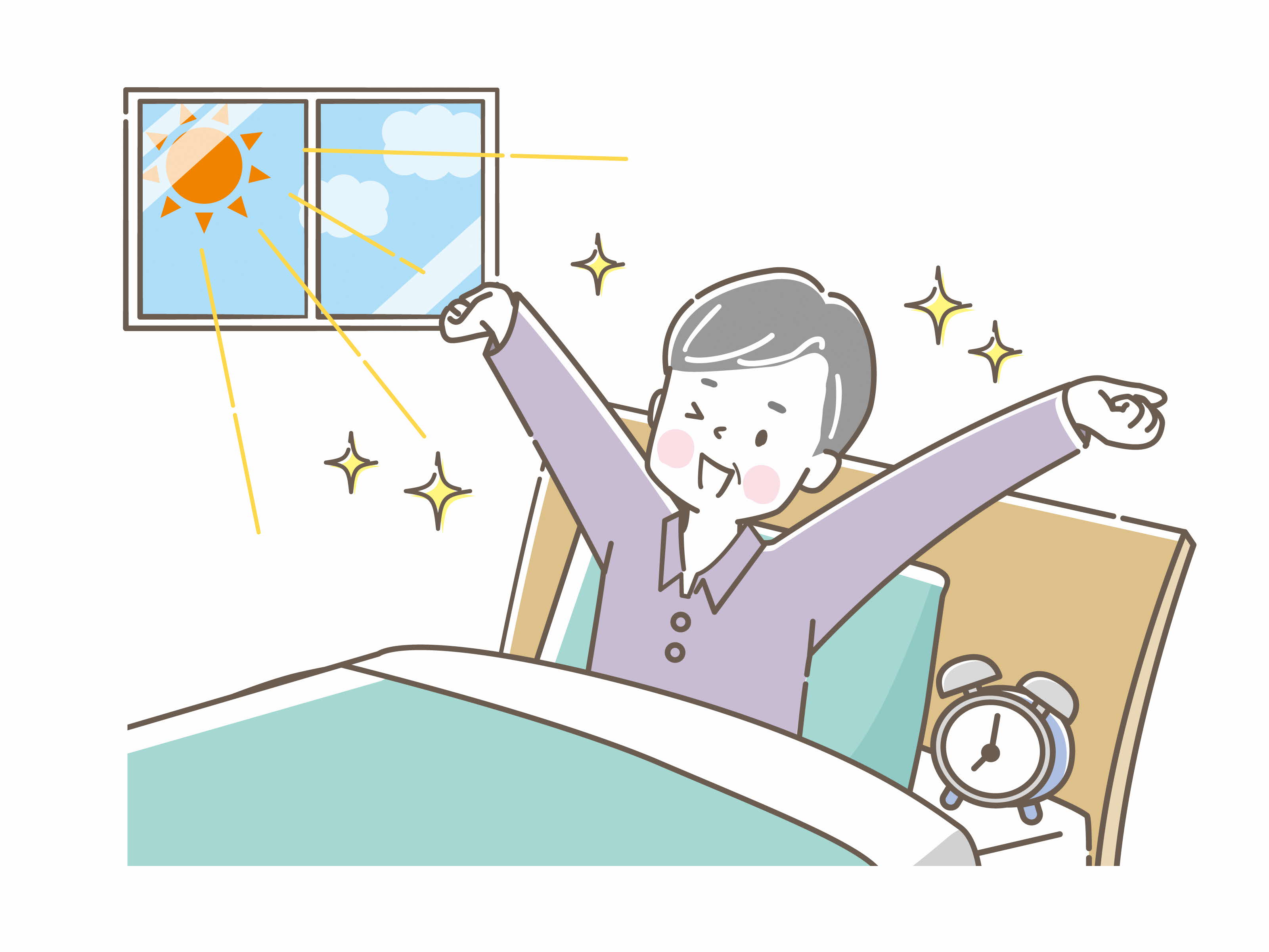 同じ時間に起きる習慣をつけることで、生活リズムをつくっていくことができます。生活リズムを整えることで、さまざまなメリットがあります。よい睡眠をとることができることもそのうちの一つです、質のよい睡眠は、疲れにくく、ストレスを溜めづらい身体づくりに効果的です。
同じ時間に起きる習慣をつけることで、生活リズムをつくっていくことができます。生活リズムを整えることで、さまざまなメリットがあります。よい睡眠をとることができることもそのうちの一つです、質のよい睡眠は、疲れにくく、ストレスを溜めづらい身体づくりに効果的です。
朝日を浴びて身体のスイッチをオンに
朝日を浴びて身体を活動モードに切り替えましょう。脳が光を感じることで体内時計の1日が始まります。良いスタートを切って、活動的に過ごしませんか?
寝る前のスマートフォンやパソコン作業は控えめに
 スマートフォンやパソコンから発せられる光によって脳が「昼間」だと錯覚します。このため、寝る前にスマートフォンやパソコンを使用すると眠りが浅いなどの原因となってしまいます。睡眠不足は疲労蓄積の原因ともなるため、寝る前はスマートフォンやパソコンを手の届かないところに置くなどして、使用を控えましょう。
スマートフォンやパソコンから発せられる光によって脳が「昼間」だと錯覚します。このため、寝る前にスマートフォンやパソコンを使用すると眠りが浅いなどの原因となってしまいます。睡眠不足は疲労蓄積の原因ともなるため、寝る前はスマートフォンやパソコンを手の届かないところに置くなどして、使用を控えましょう。
たばこは卒業
禁煙外来の受診も
 たばこを吸い続けることでさまざまな病気を発症するリスクが高まります(がん・高血圧・喘息・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・肺炎・脳卒中・心筋梗塞など)。また、たばこに含まれる「ニコチン」には依存性があり、これがたばこを簡単にやめることができない要因となっています。しかし、たばこは自分自身だけでなく、周囲の人たちの健康も危険にさらしてしまいます。自力で禁煙することに自信がない方は、医師があなたの禁煙をサポートしてくれる「禁煙外来」も検討してみてはいかがでしょうか(一定の要件を満たせば保険適用が可能です。)。
たばこを吸い続けることでさまざまな病気を発症するリスクが高まります(がん・高血圧・喘息・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・肺炎・脳卒中・心筋梗塞など)。また、たばこに含まれる「ニコチン」には依存性があり、これがたばこを簡単にやめることができない要因となっています。しかし、たばこは自分自身だけでなく、周囲の人たちの健康も危険にさらしてしまいます。自力で禁煙することに自信がない方は、医師があなたの禁煙をサポートしてくれる「禁煙外来」も検討してみてはいかがでしょうか(一定の要件を満たせば保険適用が可能です。)。
お酒の適量を知ろう
飲み過ぎに注意!就寝前の飲酒は控えて
一日の飲酒量の目安は下記のとおりです。

| 種類 | 目安 |
|---|---|
| ビール(アルコール度数 5%) | 中瓶1本(500ml) |
| 日本酒(アルコール度数 15%) | 1合(180ml) |
| ウイスキー(アルコール度数 43%) | ダブル1杯(60ml) |
| 焼酎(アルコール度数 25%) | グラス2分の1杯(100ml) |
| ワイン(アルコール度数 14%) | グラス2杯弱(200ml) |
| チューハイ(アルコール度数 7%) | 缶1本(350ml) |
※厚生労働省「健康日本21」で「節度ある適度な飲酒」とする、1日平均純アルコールで約20g程度を飲酒量に換算したものです。
※体質や年齢などによっても異なります。また、女性や高齢者はアルコール代謝が低いため、この半分の量を目安としてください。
休肝日をつくろう
週に2日は休肝日をつくることを意識しましょう。
歯と口からの健康
全身の健康は「お口」の健康から!
むし歯や歯周病が悪化すると、歯がグラグラしたり、抜けてしまったりしてよく噛むことができなくなります。また、歯周病は糖尿病や脳梗塞、心筋梗塞などの病気とも関係が深いことがわかっています。お口の健康をキープすることで、あなたの未来の健康につなげましょう。
歯と口の健康には日々のケアが肝心
「むし歯」や「歯周病」は、風邪と異なり、一度かかってしまうと自然には治りません。お口の健康は生活習慣と密接に関係していますので、下記のようなことを意識して、日々のケアから予防することが重要です。
○ 1日1回は、ていねいに歯を磨く
○ 歯と歯の間は歯間清掃具を使う
○ 定期的に歯科医院でチェックを受ける
※「自分に合った歯間清掃具で歯と歯の間をキレイにしよう!」ページで歯間清掃具の選び方や使い方を紹介しています。ぜひご参照ください。
※対象年齢に該当する場合は、足立区が実施する無料の「成人歯科健診」「後期高齢者歯科健診」を受診することができます。
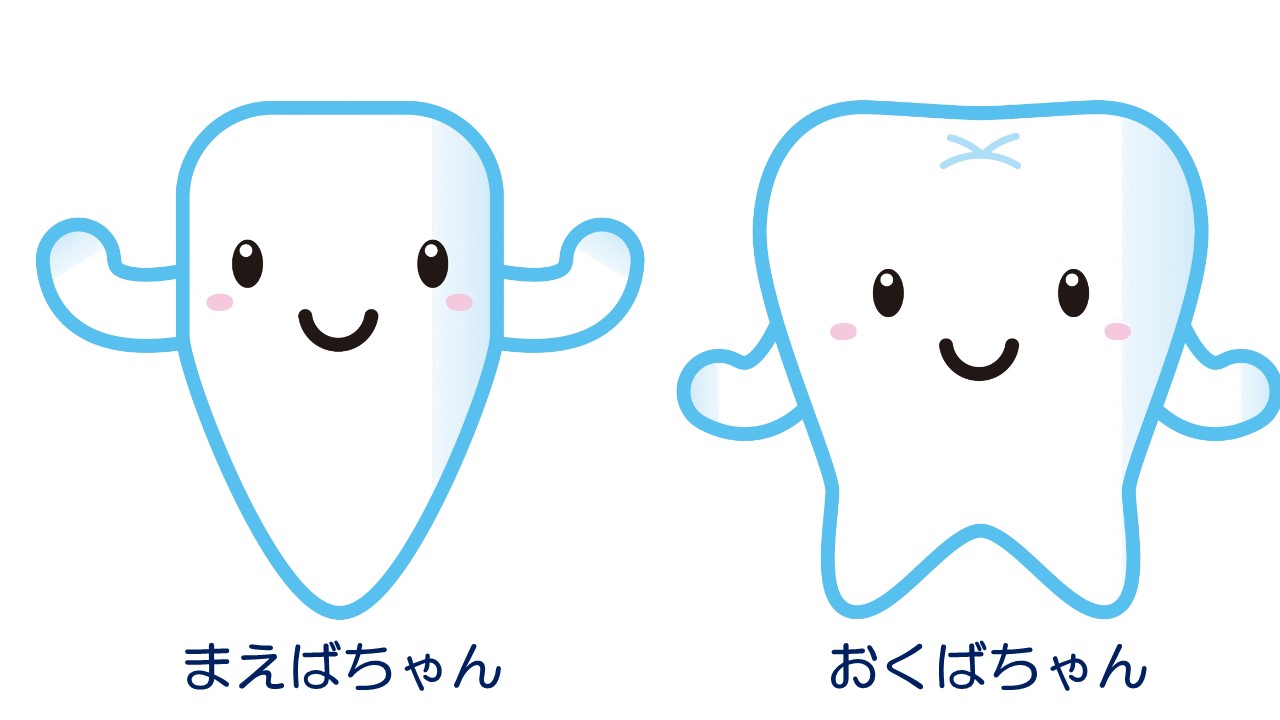
定期的な健診・検診
 足立区では、年齢や条件に応じて各種健診・検診を実施しています。
足立区では、年齢や条件に応じて各種健診・検診を実施しています。
定期的に受診することで身体の変化や現在の状況を知ることができます。どれもお得に受診することができますので、足立区の健診・検診から身体メンテナンスを始めてみませんか?
どんな健診・検診があるか「健康診査・検診のご紹介」ページで紹介しています。また、今年度あなたが受けることができる健診・検診を調べることができますので、ぜひご覧ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は