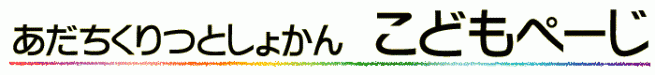ホーム > 文化・スポーツ > 足立区立図書館トップページ > こどもぺーじ > 【としょかん】かこのテーマでしらべる > かこのテーマでしらべる 2024年7月
ここから本文です。
公開日:2024年10月1日 更新日:2024年10月1日
かこのテーマでしらべる 2024年7月

としょかんには、たくさんの本があります。
そのとしょかんにある本をつかって、しらべてみよう!


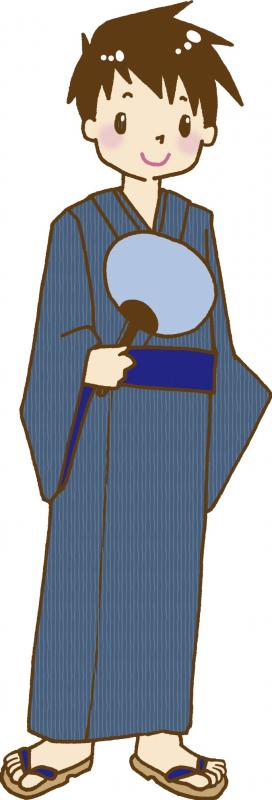

夏といえば「ゆかた」。花火大会やお祭りに行くと、きれいなゆかたを着ている人を見かけます。そこでゆかたについて、調べることにしました。
ゆかたってなに?
ゆかたは、着物のひとつで、夏に着るうすい生地の着物です。布(ぬの)はもめんでできていて、汗(あせ)をよく吸(す)います。もともとは、湯上りや寝(ね)るときなど、夕方くらいから室内で着るものでした。
着物のはじまりは?
記録(きろく)に出てくる日本人の最初(さいしょ)の衣服(いふく)は、弥生(やよい)時代です。男性(だんせい)は、一枚(まい)の布(ぬの)を体にまきつける「巻布衣(かんぷい)」を、女性(じょせい)は、布に穴(あな)をあけて、そこから頭を通す「貫頭衣(かんとうい)」を身に着けていました。
その後、裁縫(さいほう)技術(ぎじゅつ)が入ってくると、身分の高い人は上下にわかれた衣服を着るようになります。また、中国の文化を積極的(せっきょくてき)に受け入れていた時代には、中国風の衣服を着ていました。
「着物」という日本オリジナルの衣服が生まれたのは、平安時代のことです。貴族(きぞく)の服装(ふくそう)がはなやかになり、同じかたちの衣服を何枚も重ねる「十二単(じゅうにひとえ)」(おおそで)が代表的(だいひょうてき)なものです。このときに、今の着物の原型(げんけい)でもあるそで口の小さな「こそで」も生まれました。
ゆかたを着るのは大変?
ゆかたを着るには、いくつかひつようなものがあります。ゆかた、おび、はだじゅばん、こしひも、おびいたなどです。はだじゅばんはゆかたの下に着るものですが、タンクトップでもだいじょうぶです。また、おびいたは、おびの前の部分を整えるためのもので、厚紙(あつがみ)でもだいじょうぶです。
着付(きつ)けのしかたは、動画サイトで見ることができますし、着付けがひつようのない、べんりなゆかたもあります。また、ねだんの安いゆかたもあります。
ゆかたのおしゃれ
「ゆかたのおしゃれ」は、ゆかたやおびの色・柄(がら)だけではありません。髪型(かみがた)をかえたり、ビーズや端切(はぎ)れなど100円ショップや家にあるものを使って、ゆかたに合う小物を手作りすることもできます。かんたんにできるものがのっている本を下に書いておきますので、参考(さんこう)にしてみてください。
調べる前のゆかたの印象(いんしょう)は、「着るのがむずかしそうだし、ひつようなものをそろえるのにお金がかかりそう」でした。しかし、身の回りにあるもので代用できるものもあることや、安く手に入れられることがわかりました。また、100円ショップなどにあるもので小物を作れば、ひとくふうできそうですね。
このページの内容は
1『再発見!くらしのなかの伝統文化 1』 市川寛明/監修 ポプラ社
2『「日本人」を知る本 人・心・衣・食・住 3』 岩崎書店
3『調べて、くらべて、考える!くらしの中の和と洋-着る-』 岡部敬史/編著 汐文社
4『楽しむ伝統文化 着物 3』 織田きもの専門学校/監修 保育社
を参考に、小学生にもわかりやすいよう、一部編集したものです。
「もっといろいろ知りたいな」という人は、ぜひ図書館に来てこれらの本を読んでみてください。
↑しらべ学習のしかたを知りたいときは、上をクリックしてね。
↑かこのテーマいちらんに戻りたいときは、上をクリックしてね。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は