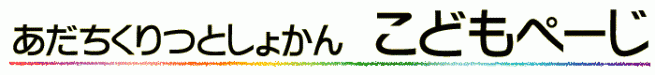ホーム > 文化・スポーツ > 足立区立図書館トップページ > こどもぺーじ > 【としょかん】かこのテーマでしらべる > かこのテーマでしらべる 2024年4月
ここから本文です。
公開日:2024年7月1日 更新日:2024年7月1日
かこのテーマでしらべる 2024年4月

としょかんには、たくさんの本があります。
そのとしょかんにある本をつかって、しらべてみよう!


春は学校へ入学したり、ひとつ上の学年に上がるなど、新しい1年がはじまる季節(きせつ)ですね。そこで今回は、学校(小学校)のはじまりとその歴史(れきし)について調べてみました。
学校のはじまり
日本にはじめての学校ができたのは、7世紀(せいき)後半のころといわれています。でもその時の学校は役人を育てるための学校だったので、身分の高い人の子どもしか入学できませんでした。ふつうの家の子どもが通う学校は、平安時代に空海(くうかい)というお坊(ぼう)さんがつくった「綜芸種智院」(しゅげいしゅちいん)という学校がはじまりとされています。ただで勉強ができましたが、子どもたちは生活のためにはたらいていて、勉強できるチャンスはほとんどありませんでした。
寺子屋(てらこや)
江戸(えど)時代になると、ふつうの家の子どもも、読んだり書いたりする力が必要(ひつよう)になってきました。そこで勉強をする場として、寺子屋がつくられました。子どもたちは家の手つだいをしてから寺子屋へ通い、師匠(ししょう)とよばれる先生から、文字の読み書きやそろばんを習いました。寺子屋では、勉強の進みぐあいに合わせて1人1人見ていくので、みんながべつべつの勉強をしているのがふつうでした。ちなみに、行かなくてはいけない決まりはなかったので、寺子屋に通っていない子もいました。
寺子屋から小学校へ
明治(めいじ)に入ると、6歳(さい)になったすべての子どもを学校に通わせることを決めた「学制」(がくせい)という法律(ほうりつ)ができ、全国に小学校がつくられました。ところが、生活のためにはたらいていたり、授業料(じゅぎょうりょう)がはらえないなどの理由で、小学校へ通う子どもは全体の半分より少なかったそうです。政府(せいふ)が学校に通わせるようにはたらきかけたり、新しい法律で授業料がなくなることが決まると、ほとんどの子どもが小学校へ通うようになりました。
戦争(せんそう)中の小学校
昭和のはじめに戦争がはじまると、小学校は国民学校(こくみんがっこう)という名前にかわりました。そして今までの勉強ではなく、日本のためにはたらいたり、戦争に協力(きょうりょく)することが大切だと教えるようになったのです。戦争がはげしくなると、たくさんの家や小学校がやけてしまいました。そこで子どもたちは親とはなれ、先生といっしょに危険(きけん)の少ない地方へ移る「疎開」(そかい)をしてお寺などで勉強をしました。
現在(げんざい)の小学校へ
戦争が終わると、社会がかわり学校もかわりました。国民学校から小学校に名前がもどって、戦争に関係(かんけい)のある勉強をすることはなくなりました。そして新しい法律ができ、すべての人が教育を受けられることや、小学校と中学校の9年間が義務(ぎむ)教育となることなど、今の小学校につながるルールが決まりました。たくさんの学校が焼けてしまい先生も足りないなど、はじまりは大変(たいへん)なことがたくさんありましたが、それを乗りこえて現在につづいているのです。
調べてみると、だれでも通える小学校のはじまりは、あまり昔ではないことにおどろきました。では、ランドセルや給食(きゅうしょく)など、今では当たり前にあるもののはじまりはどうなのでしょうか?気になった人はしらべてみてくださいね。
このページの内容は
1『総合百科事典ポプラディア 4』 ポプラ社
2『21世紀こども百科もののはじまり館』 小学館
3『日本はじめて図鑑 身近な「もの」のはじまりがわかる』 田中裕二/監修 ポプラ社
4『にほんのもと 学校』 齋藤孝/監修 講談社
5『ビジュアル版学校の歴史 3』 岩本努・保坂和雄・渡辺賢二/共著 汐文社
6『日本の生活100年の記録 3』 佐藤能丸・滝澤民夫/監修 ポプラ社
7『4つの時代をタイムトラベル 日本の歴史を楽しく学ぼう! 1』 大串潤児/監修 廣済堂あかつき
8『テーマで調べるクローズアップ!日本の歴史 8』 ポプラ社
9『くらべてみよう!昭和のくらし 2』 新田太郎/監修 学研
を参考に、小学生にもわかりやすいよう、一部編集したものです。
「もっといろいろ知りたいな」という人は、ぜひ図書館に来てこれらの本を読んでみてください。
↑しらべ学習のしかたを知りたいときは、上をクリックしてね。
↑かこのテーマいちらんに戻りたいときは、上をクリックしてね。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は