ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 教育委員会 > こんにちは、教育委員です!-教育委員会委員の活動紹介- > 令和7年7月の教育委員の活動報告
ここから本文です。
公開日:2025年8月26日 更新日:2025年8月26日
令和7年7月の教育委員の活動報告
令和7年第7回足立区教育委員会定例会を開催しました!
令和7年7月14日に令和7年第7回足立区教育委員会定例会を開催しました。本定例会には、7件の議案が付議され、審議の結果全て可決されました。また、「令和7年度実用英語技能検定受験支援事業の実施状況について」や「不登校に関する児童・生徒及び保護者アンケートの実施について」など、7件の報告を行いました。
可決された議案と内容の一部をご紹介いたします。
【議案名】
足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則の送付について
【内容】
社会人を対象とした奨学金返済支援助成制度の創設などに伴い、足立区育英資金条例を改正したことを受け、足立区育英資金条例施行規則を改正するもの。
【議案名】
足立区民設学童保育室設置促進補助金交付審査会委員の委嘱及び任命について
【内容】
足立区民設学童保育室設置促進補助金交付審査会委員を委嘱及び任命するもの。
教育委員からの質問をピックアップしてご紹介します!
【土肥委員からの質問】

「令和7年度実用英語技能検定受験支援事業の実施状況について」
質問内容:実用英語技能検定の受験費用について、令和6年度から中学3年生を公費対象とし、令和7年度は中学1年生、中学2年生にも対象を拡大するということで、非常に良い事業だと思う。しかし、取りまとめや申込みのチェックを行う教員の負担が大きいため、業務フローの改善を考えていただきたい。
担当課からの回答:今年度は対象者の学年が多岐に渡ることもあり、英語科教員の方々にいろいろな面で負担をかけていると捉えている。今後の申込み等については、効率化、簡略化できないかどうかを検討する。
【その他の主な質問】
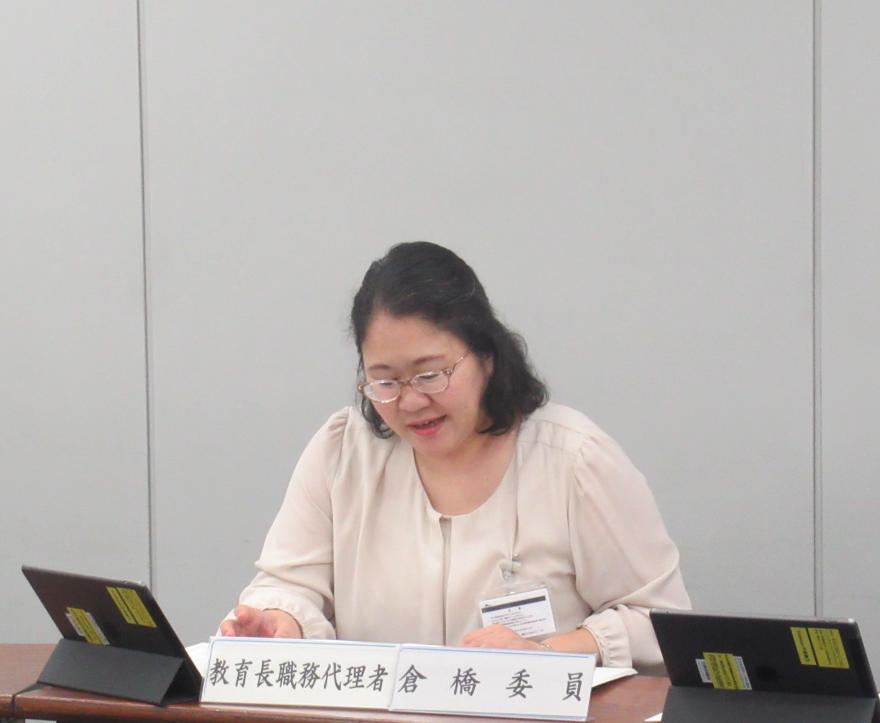
↑「不登校に関する児童・生徒及び保護者アンケートの実施について」について、このアンケートの目的は不登校の児童・生徒の実態と要因を分析し、その支援策を講じることであるから、不登校の子に回答してもらうことが大切である。そのため、負担は増えてしまうが、ぜひ学校の教員やSSW(スクールソーシャルワーカー)の方に対象者の自宅を訪問していただき、アンケートを渡してもらいたいと話す倉橋委員。
青少年委員との教育懇談会に参加しました!
令和7年6月から7月にかけて区内13ブロックの青少年委員と学校関係者らがそれぞれの地域の実情や課題などの共有・協議を行う教育懇談会があり、教育長と教育委員が参加してきました。その中の一部をご紹介します。
【第6ブロック(綾瀬小、東綾瀬小、東綾瀬中、蒲原中など9校)】
第6ブロックには中村教育長が参加しました。会全体のテーマとして『今後の青少年委員の在り方』を掲げ、講師である足立区青少年委員会会長から「地域の繋ぎ役だから主役になれる」をテーマに講演があり、参加者による意見交換が行われました。
講師からは、長年の青少年委員としての活動を踏まえ、青少年委員の位置付けや活動内容、青少年委員と学校・開かれた学校づくり協議会等との連携や役割分担によりもっと子どもたちを支えていくことができるのではないかとの話がありました、また、学校側の、青少年委員の位置付け・役割に対する認識が不足している可能性があり、青少年委員を活かしきれていないのではないかとの提言もありました。

↑教育懇談会への招待に対する御礼、こういった懇談会での情報共有等の重要性、最近発生した少年非行事案を引き合いに青少年委員会と教育委員会が連携・協力し、地道に子どもたちとの繋がりを構築していくことで未然防止に努めていきたいとの考えを話す中村教育長(中央起立者)
【第5ブロック(足立小、弥生小、第四中、第十一中など6校)】
第5ブロックには土肥教育委員が参加しました。『子供たちと笑顔あふれる地域を目指して!』を議題として、(1)子供たちの現状と課題について、(2)各小中学校における地域との連携について、(3)【育ちの教育】の中で失ってはいけないモノの3点について参加者からの発表と意見交換が行われました。
参加者からの発表においては、PTAの加入者数低下に伴いPTA活動をボランティア制に転換した事例や、情報通信機器の発達・普及に伴い、いつでも容易に情報を取得することができるようになったことから、児童・生徒が人と人との対面において相手の話を聴く力が低下しているとの心配の声も聞かれました。一方で、あだち放課後子ども教室は、地域の遊び場不足を補い、コミュニケーション能力を養う場としても機能しているとの声が聞かれました。

↑自身が五反野小学校(現在は千寿第五小学校との統合により足立小学校)において副校長及び校長として地域と関わった経験から、地域(町会)、PTA、学校が同じ方向を向いて児童・生徒の健全育成に取り組むことの有効性について話す土肥教育委員(中央起立者)
【第8ブロック(青井小、栗島小、青井中、栗島中など8校)】
第8ブロックには大井教育委員が参加しました。会の前半は都立特別支援学校(知的障害)教諭、兼ユニバーサルスポーツクラブゆにぽすキッズ代表である神保様から「学校と地域で育む『共生社会』子供たちが生き生きと輝くコミュニティづくり」をテーマにご講演いただき、後半は参加者全員でボッチャを体験しました。
神保様からは、共生社会を見据えたインクルーシブ教育について、障がいがあっても同年齢の子どもと同じ場(通常の学級)で学べる教育システムというイメージをもたれやすいが、実際は通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意することが重要であるという話がありました。
神保様は障がいの有無に関わらず、多様な子どもたちが一緒に過ごせるコミュニティを作りたいと「ユニバーサルスポーツクラブゆにぽすキッズ」を設立され、ボッチャ等を通じて障がいのある児童生徒が活躍する機会を増やすべく、体験会や大会を企画しているとのことでした。

↑ボッチャのボールを投げる大井教育委員
【第10ブロック(渕江小、中島根小、渕江中、六月中など9校)】
第10ブロックには倉橋教育委員が参加しました。会では市民防犯インストラクターである武田様から「みんなで学ぶ子どもたちと地域の安全」をテーマにご講演いただき、最後に参加者全員で防犯体験をしました。
武田様からは、犯罪が起きにくい環境を作るためには、警察による防犯だけでなく市民による防犯が重要であり、特に子どもを狙う犯罪は人の目があると犯意を出しにくいため市民防犯が有効という話がありました。現在は防犯活動のスタイルも多様化しており、買い物やウォーキングの際などに子どもたちへ目を向ける「ながら見守り」という形もあるので、無理なく取り組んでほしいとのことでした。防犯体験では、心理的な距離の確認や防犯ブザーの使い方の確認を行いました。

↑自身が務めていた小学校PTA連合会の立場からも子どもへの見守りが重要であると話す倉橋教育委員(右側起立者)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は


